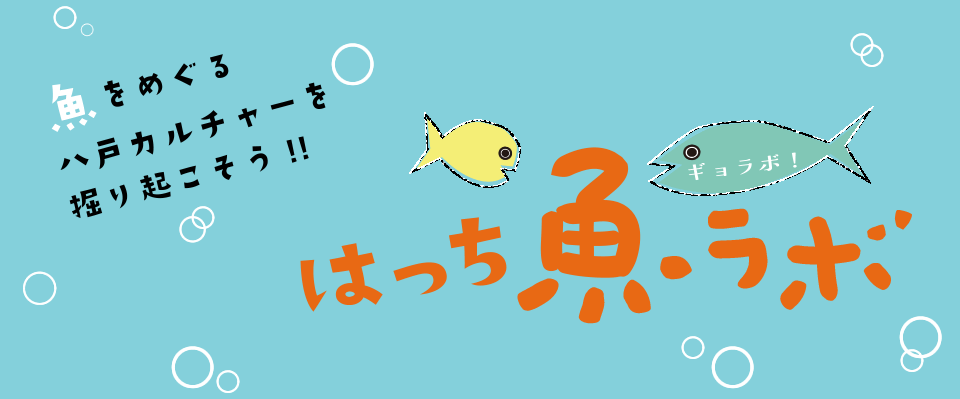【報告】第7回魚ラボ会 八戸の海辺のくらしを見つめ直す
カテゴリー:魚ラボ会
12月13日(土)、八戸市博物館学芸員の小林力さんをゲストにお迎えし、第7回目の魚ラボ会を開催しました。
小林さんは岩手県宮古市出身。関西の大学で学び、滋賀県長浜市に学芸員として勤務後、昨年4月から八戸市博物館の民俗担当の学芸員として、三陸に戻ってきました。得意分野は「生業」と「文化的景観」。「文化的景観」とは、人が生活や仕事をする中で作り出した景観のことです。棚田や防風林などがそれに当たりますが、八戸の海辺でいえば、防潮林や放牧地として利用された種差芝生地、海岸段丘上の集落などがそれに当たります。
小林さんは、かろうじて津波の被害を免れた大久喜の浜小屋(国指定重要民俗文化財)に収蔵されている貴重な漁撈用具を紹介してくれました。なんと、タチアマモという海藻で作ったというミノ!海藻で雨風を凌いだのです。カモシカの角で作ったというイカの釣り漁具は、まるでアクセサリーのように美しいではありませんか!材料を漁具屋さんに持って行き、細かい部分の造りを指示して作ってもらったのだそうです。麻を煮て繊維をとり、それを編んで漁網を作るなど、漁師さんたちは海に出て魚を獲る仕事だけではなく、かなり繊細な作業をしてきたことがわかりました。
博物館に収蔵されている約8000点の写真資料の中には、海辺の人たちの暮らしや風物をとらえた作品もたくさんあります。刊行されている「なつかしの八戸 -和井田登 寄贈作品より-」に掲載されている昭和30年〜40年代の八戸の砂浜は、今よりずっと広々と見えます。その大きな砂浜を埋め尽くす「スルメのカーテン」や煮干しを作るためにイワシを乾燥させるおびただしい数の箱。かつての浜の賑わいがどれほどのものだったかを、これらの写真の数々は語ります。

魚ラボ編集部が感動したのは、浜の人たちの地域での互助の伝統です。集落の人たちがみんなで行うコンブ採りやコンブ干し、ウニの一斉採りの収益は分配されたり地域のものとなり、一部は一家の大黒柱を失った家の人を助けたり、共同体共有の財産を維持保全したりしてきたということでした。その互助のしくみは、今も生きています。まさに、種差海岸一帯の美しい景観は、こうした海辺に暮らす人たちが、日々海を守り使い続けることで生まれた風景なのだと確信した瞬間でした。
さらに海辺に住む人びとの生計が、必ずしも漁業に依存していないということも驚きでした。多くの家が農業を行い、一方で漁業や加工業をおこなってきました。しかしみんなが同じだったわけではなく、漁業がメインか農業がメインか、それともソレ以外がメインか、バランスの取り方は家によって異なりましたし、時代に合わせて変わってもきました。海辺の人たちは、このように多角経営をしながら、人間の思い通りにはいかない大自然を相手に、持続可能な生業のあり方を模索してきたのです。
海との関わり方も多様で、専業で漁をする家もあれば、コショウバイといって自給用の食材を採る漁や一斉採りだけ参加する家もありました。もちろんコショウバイをする方々も地元に住み、漁業権をもち、港や水産資源を管理利用する人たちです。小林さんのお話から、高齢化によって、「コショウバイ」を行う人が減少し、海と関わりを持つ人が減り、海への関心も薄れているということを痛感もしました。海のそばに住みながら、海は遠くなっているのです。
海を守り使う人々がいるから、八戸の海は美しいのです。小林さんのお話に、宮本常一の『自然は寂しい、しかし人の手が加わると暖かくなる』という言葉を思い出さずにはいられませんでした。